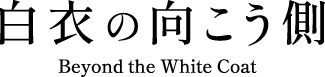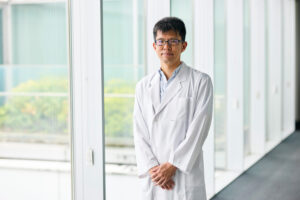新見正則医院 院長新見 正則(にいみ・まさのり)

医学は、時にくじ引きゲームのようだ。
大多数の集団に対して有効な治療法が存在しても、それが個々の患者に完全に当てはまるとは限らない。
つまり、現代の医療には、はずれクジが存在している。
外科医として、研究者として――新見正則医師はその迷路を歩きながら、医学の「隙間」にある可能性を拾い上げてきた。
幼少期のどもりと読後障害。その経験は、「話す前に聴く姿勢」を身体に刻んだ。言葉よりも先に、表情、沈黙、息づかいを受け止める感覚。それは医師としてのスタイルの源流となった。
医学を志した当初から、新見医師の視線は常に「患者の先」にある。治療という行為だけでなく、患者の未来に責任を持つ。そのためには、学び続け、問い続けなければならない――。その思いが、やがて日本から世界へと向かうきっかけとなった。
外科医として積み上げた現場と技術
慶應義塾大学医学部を卒業後、同大学病院外科で研鑽を重ねた。
外科医として歩み始めた初期、彼の前に立ち上がったのは「医学は原則から始まる」という厳然たる事実だった。
ガイドライン、標準治療、統計データ──それらは医療の基盤であり、無視して成立する臨床など存在しない。
「統計値や一般論を軽視することはありません。医学はまず“守る”ことから始まります。先人の知と膨大な臨床データの蓄積があるからこそ、医療は迷わず診断と治療へ踏み出せる。」
そう話す口調は穏やかだが、その裏には経験から来る揺るぎのなさがある。
しかし外科の現場では、教科書どおりに進まない症例に必ず出会う。出血量、予測外の解剖、術後の反応、全身状態の変化──そこには統計では語りきれない「一人の患者としての差異」が横たわっている。

その矛盾と向き合い続けた日々が、新見医師にひとつの理解を与えた。
「臨床は“型を守ったうえで”はじめて破り、最後に患者さんに合わせて離れていくものです。目の前の一人に届く医療を考えると、確率論だけで治療は設計できない。」
その言葉には、医療の理論と患者のリアルを両手で抱えてきた外科医としての重量がある。
「医学は成功の頂点だけを見せて成立するものではありません。その裏側には、仮説、検証、修正の繰り返しがあり、その積層こそが臨床の“納得”につながる。」
そう語る眼差しには、外科医として過ごした時間が深く刻まれている。
そしてその哲学は、研究へ、さらに新しい治療選択肢の探究へと引き継がれていく。
オックスフォード大学 ― 研究者としての視座を確立した場所
外科医として現場の判断と身体感覚を積み重ねた先に、新見医師はもう一つの問いに向き合うことになった。
「この治療は、なぜ効くのか。そして同じ疾患でも、なぜ患者によって反応が違うのか。」
その問いを深めるため、1993年、英国・オックスフォード大学医学部博士課程へ進む。
テーマは移植免疫学。移植免疫、炎症、サイトカイン、免疫応答の階層構造――生命と疾患の間にある複雑な機構を、紐解く研究だった。

オックスフォードでの研究文化は、日本で経験してきた臨床現場の緊張とはまったく異なる種類の厳しさを持っていた。仮説は容赦なく批判され、実験結果は第三者の再現性を前提に評価される。感覚や経験は尊重されるが、証明なしに受け入れられることはない。
新見医師はそこで痛感する。
「臨床が“人を救う医学”なら、研究は“問いを曖昧にしない医学”だ。」
外科医としての経験では、多くの治療は統計的裏付けや標準治療を基盤としながら運用される。その重要性は揺るがない。
しかし研究の世界で向き合った免疫系は、単純な因果では測れない揺らぎと多層性を持つシステムだった。
西洋医学の根幹を支える単一成分の薬剤が「標的を一点で叩く」考え方だとすれば、免疫応答は複数の回路が網目状に連動し合う世界であり、その働きを調整する作用は必ずしも単純化できない。
その理解は、新見医師の中に一つの視座を形成する。
「医学はまず“型を守る”。しかしその先には、“例外に向き合う医療”が存在する。」
外科医として培った「目の前の患者を救うための決断」と、研究者として身についた「複雑性を受け止め、検証し続ける姿勢」。

その両輪が、新見医師の医療観をより立体的なものにしていった。
免疫は単純ではない。
疾患も治療反応も、患者ごとに揺らぐ。
その揺らぎを否定せず、科学として扱うこと――その思想は、のちに多成分系薬剤との出会いにつながっていく。
生薬「フアイア」との出会い ― 医学の境界を越える研究として
日本へ戻り、外科診療と教育、研究指導に携わっていた頃、ひとつの論文が新見医師の視界に入る。
英国の医学専門誌『GUT』に掲載されていたその研究は、肝臓がん術後患者1,000例以上を対象とした生薬「フアイア」の臨床データだった。

最初に目にしたとき、新見医師は「代替医療としての興味」ではなく、研究者としての好奇心と臨床医としての責任感で読み進めた。
効果の有無ではなく、なぜ結果が出たのか。
どの経路が関与したのか。
再現性はどこまで担保されているのか。
自然と問いが立ち上がった。
生薬や漢方は長い歴史がありながら、現代医学ではエビデンスのないもの。つまり科学としての検証方法が単一成分薬とは異なることが課題とされてきた。
複雑な成分の集合体であるがゆえに、標的分子や作用経路の説明は容易ではない。
しかし、それは“証明できない”のではなく、“証明するためのモデルが未整備である”だけかもしれない。
オックスフォードの研究室で培った多層的免疫理解が、ここでひとつの仮説へと結びつく。

「単一成分では説明しきれない作用であっても、生体側の複雑性に適応する形で働いている可能性がある。」
科学者としての姿勢は変わらない。
疑うことから始める。
しかし、否定で終わらせない。
新見医師は次の問いを自らに投げかけた。
「もし臨床的に意味があるのであれば、患者の選択肢として提示できるべきではないか。」
新見医師が最初に行ったのは「信じる」ことではない。調べることだった。
文献、データ、症例経過。
作用仮説、濃度、代謝、相互作用。
既存学術体系の外側に置かれていた情報を整理し、ひとつの医学的言語へ翻訳する作業を続けた。
その背景には、医師×サイエンティストとしての哲学がある。
「医学は白黒よりも、時に“まだ灰色”の領域に意思を持って向き合う必要がある。」
治るかどうかではなく、
効くかどうかではなく、
目の前の患者にとって意味があるか。
その視点が、新見医師の判断軸となった。
開業 ― 選択肢のある医療を患者に届けるために
大学病院で診療に携わる中で、新見医師は標準治療が果たす役割と、その強度を十分評価していた。
プロトコールに沿った治療は、医学の安全性と再現性を支える重要な仕組みであり、多くの患者にとってもっとも合理的な選択肢となる。
その体系は、膨大な臨床データと研究の積み重ねが保証する“全体最適の医療”だ。
しかし、外科医として数えきれない患者と向き合う中で、新見医師はひとつの現実を見続けることになる。
「平均点が最も高い治療は、多くの人を救う。けれど、平均から溢れる患者が確かに存在する。」
疾患の進行、体質、免疫反応、生活背景、治療への価値観――
教科書や統計では扱いきれない“個別性の揺らぎ”を前にしたとき、プロトコールが示す正解は必ずしもその患者にとっての正解とは限らない。
その現場に、矛盾があった。
診療は効率化され、治療は均霑化されていく。
患者は医療の合理性の中で救われる一方で、「なぜ自分は当てはまらないのか」という声は、合理化の陰へ押し出されていった。
新見医師は、その矛盾を責めることはしない。
むしろ、それが現代医療が到達した高度な仕組みであることを理解している。
しかし、同時にこうも考えた。
「医療の目的は、最大公約数としての正解ではなく、目の前の一人が納得して生きられる治療を探すことではないか。」
その思考が、研究者として培った視座と結びつく。
オックスフォードで学んだ免疫学、多成分系薬剤への理解、そして帰国後に出会った生薬フアイアの臨床データ。
それらは線ではなく、点として存在していた。
しかしある時、それらは自然とひとつの方向を指し示す。
「標準治療だけでは届かない領域に、医療として向き合う余地がある。」
その気づきは、開業という形に結晶化していく。
2020年、新見医師は新見正則医院を開設する。
目的は単純ではない。
治療を増やすためでも、医療の枠を乱すためでもない。
それは――
既存医療の隙間に置き去りにされてきた患者の声に応答するための場所。
そして、生薬フアイアをはじめとする選択肢を科学として、臨床として検証し、必要とする人に届けるための場所。

新見医師は言う。
「医療は治し方を押しつけるものではなく、その人がどう生きたいかを軸に選択をともに考える作業です。」
標準治療が“守”であるなら、
個別性に向き合う医療は既存の医療制度からの“破”であり、
患者と共に歩む治療は“離”の領域にあるのかもしれない。
その静かな思想こそが、
新見正則医院の始まりであり、今も灯り続けている理由である。
Serendipity──偶然の発見を受け入れ、科学として扱う勇気。
新見 正則(にいみ・まさのり)
慶應義塾大学医学部卒業後、同大学病院外科に勤務。外科医として臨床経験を積んだのち、1993年より英国オックスフォード大学医学部博士課程へ進み、免疫学研究に従事。1998年、同大学より博士号(Doctor of Philosophy)取得。帰国後は帝京大学医学部にて移植免疫学・血管外科学・東洋医学の教育・研究・診療に携わる。2020年、新見正則医院を開設。抗がんエビデンスを獲得した唯一の生薬「フアイア」を軸に、標準治療と科学的検証を進める多成分系薬剤の両視点をもとに、患者の価値観を軸とする医療の実践と研究を続けている。